受け継がれる秋の風習「お月見泥棒」
――月の使者と呼ばれた子どもたちと、地域の優しさ――
十五夜の夜、まんまるのお月さまが顔を出すころ。名古屋市緑区・徳重のあたりでは、今も「お月見泥棒(つきみどろぼう)」という、少し不思議であたたかな風習が残っています。
「お月見泥棒」とは、中秋の名月に飾られていたお供え物を、子どもたちが“盗む”風習のこと。昔は、子どもたちは“月からの使者”と考えられており、この日に限ってお供え物を盗むことが許されていたそうです。
お供え物を子どもたちに盗まれると縁起が良い、農作物が豊作になるといわれ、月に感謝し、収穫を祈る行事として親しまれていました。

現代の「お月見泥棒」は、静かに形を変えながら地域に受け継がれています。十五夜の午後3時ごろから夕方にかけて、家々の玄関先にはお菓子がそっと置かれます。
学校から帰った子どもたちは、リュックや袋を手に「やったー!」「あった!」と笑顔でお菓子を見つけてまわります。声をかけ合うわけではないけれど、子どもたちの楽しそうな声と、それを見守る地域のあたたかさが夕暮れの空気に広がります。
まるで日本版ハロウィンのようですが、そこにあるのは“地域で育まれる思いやり”そのものです。
家の前に置かれたお菓子、月の光に照らされた子どもたちの笑顔。その光景は、昔からこの地域で大切にされてきた「感謝」や「つながり」の象徴のようです。

お月見泥棒は、決して派手なイベントではありませんが、“顔の見えるつながり”が少しずつ薄れていく今だからこそ、こうした地域の小さな温もりが、とても尊いものに感じられます。
お月見泥棒の実施は地域ごとに異なり、外部からの参加を目的としたものではありません。もしこの時期に徳重エリアなどで、玄関先にお菓子が置かれている風景を見かけたら、ぜひ静かに見守ってくださいね。
今年の行事は終わりましたが、また来年の秋、月の光の下で子どもたちの笑い声が聞こえることでしょう。

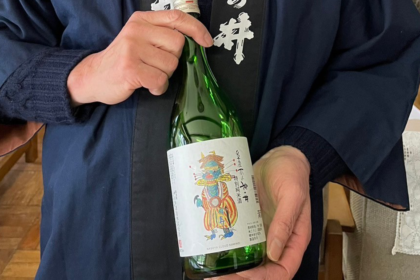




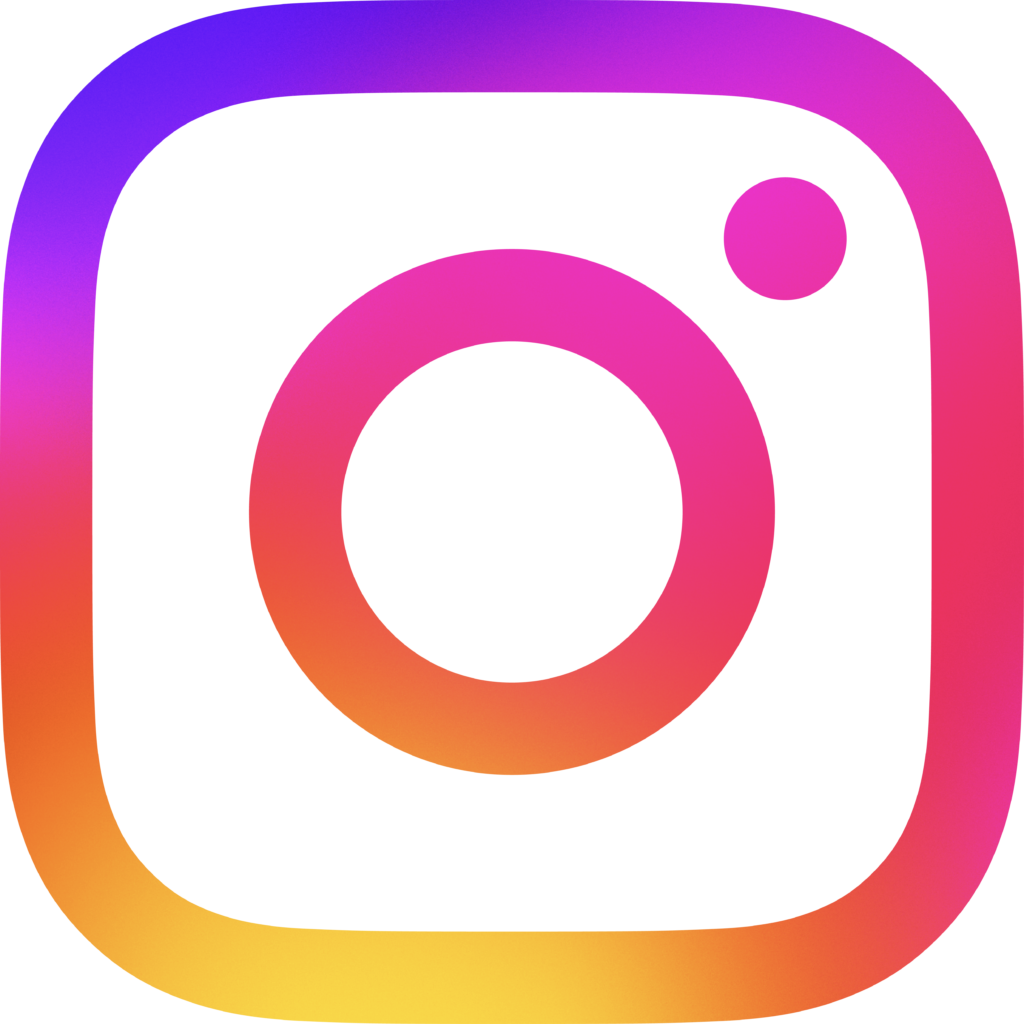





コメントを残す